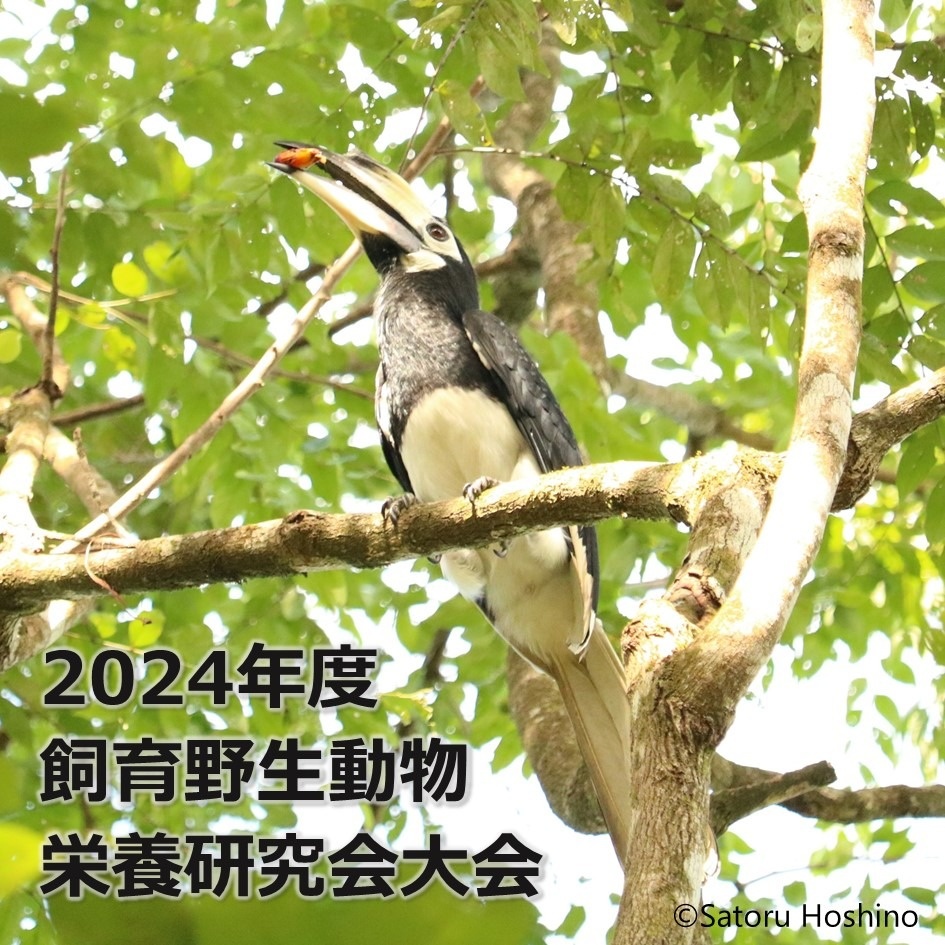2024年度大会参加のお礼
2024年度,「飼育野生動物栄養研究会」神戸大会に,ご参加いただき,誠にありがとうございました。 今回の研究会では,飼育下の野生動物における栄養管理や健康維持の方法,のみならず世界各地のフィールドで得られた貴重な知見等,多岐にわたるテーマが取り上げられ,参加された皆様の豊富な知識や実践的な経験が共有される貴重な機会となりました。学術的なアプローチのみ,現場での取り組み事例や課題についても率直に意見が交わされ,より立体的かつ総合的に「飼育野生動物の栄養」を考えることが出来たのではないかと感じております。
1980年代中ごろに,インドネシアのモルッカ諸島に生息する大型のオウムのオオバタンが急激に減少しているという情報があり,その繁殖に取り組んだことがあります。なんとか雛が孵化するのですが親が育てず人工育雛に矛先を変えました。国内初の人工ふ化個体に対して散々議論して用意した仕様を,私がチューブで与えた瞬間,喉に詰まらせて死亡。今もその時の雛の感覚が手のひらに残っています。数年間に何度かの失敗を重ね,まずはペット用のミルクを与えて初期を乗り切り,徐々に濃度を上げることで雛が育ちました。現在では,市販のオウム育雛用の飼料が輸入されており容易に雛を育てることが可能となり隔世の感があります。当時,姫路セントラルパークの飼育課長だった佐藤哲也が「雛には乳糖の分解酵素がないから危険だ。」と忠告してきましたが,上手く行ってんだから問題なしと撥ねつけたのも良い思い出です。栄養や給餌方法に関する最新の研究成果は,飼育動物の健康維持や繁殖成功への具体的な解決に向けて重要な切り口となります。それぞれの種や分類群の特徴を踏まえ,更なる研鑽が必要と考えます。
本研究会が,研究成果の発表や共有だけでなく,現場や大学・研究機関,関連企業など,さまざまな立場の方々が意見交換を行うことで,学術的にも野生動物飼育の実践にも意義のあるネットワークを形成することに意義があると感じます。飼育下の野生動物の栄養管理の充実は,動物福祉の向上や種の保存のために重要です。一つの取り組みが多様な課題解決の最終緒得となるため,今後も皆様のご協力をいただきながら,学術研究と現場橋渡しの場としての意義を深めることを切に希望するものです。最後に,発表者ならびに座長の方々にお礼申し上げ,挨拶とさせていただきます。
日橋 一昭(神戸どうぶつ王国 園長)