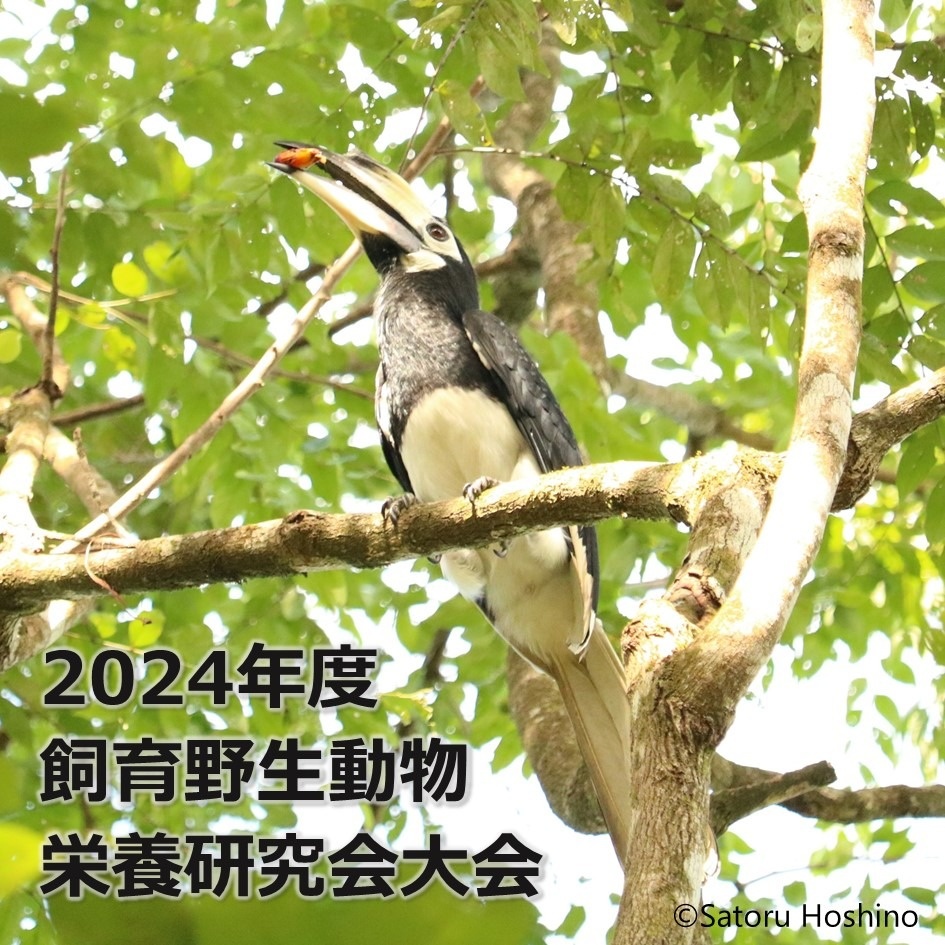書籍紹介『文明に囚われた動物たち:動物園のエソロジー』
著:H. ヘディガー
翻訳:今泉吉晴, 今泉みね子
1983年出版。思索社。
〇紹介(日橋一昭氏・神戸どうぶつ王国)
「動物園生物学」の祖H.ヘディガー著の「文明に囚われた動物たち」が日本語に訳され出版された時,そのシニカルな邦題に違和感を感じてからすでに40年以上経過している。そもそも邦訳されるさらに40年以上も前の1942年にWildtiere in Gefangenschaftという題でドイツ語で出版され,1964年に英訳されたWild Animals in Captivityが出ている。直訳の「飼育下の野生動物」ではインパクトが足りないので出版社の意向があったと聞く。
80年も前に出版され,邦訳物もとっくに絶版になっている図書を紹介するにやや躊躇いを感じるがいたしかたない。
ヘディガーは1938年から1973年にかけてスイスの3か所,ベルン・バーゼル・チューリヒ動物園の園長を歴任している。櫃者は1974年にヘディガーが辞めたばかりのチューリヒ動物園を訪れる機会を得た。最も印象に残っているのは,カバ・クロサイのパビリオンの室内展示にあるカバのプールにはアマサギ,クロサイのパドックにはウシツツキが同居しており驚かされた。著作のなかでも述べているように動物舎は囚われの動物たちを収容する場ではなく,そこにすむ動物たちの守るべき領域であるという視点,闘争距離と臨海距離などのキーワード,なによりも動物舎にとって重要なことは広さ等の「量」よりも構造等の「質」が重要と説いている。今なお,動物園本としてその輝きを失わずにいる。図書館で手に取るなり古本を探して入手する価値は十分にあるだろう。